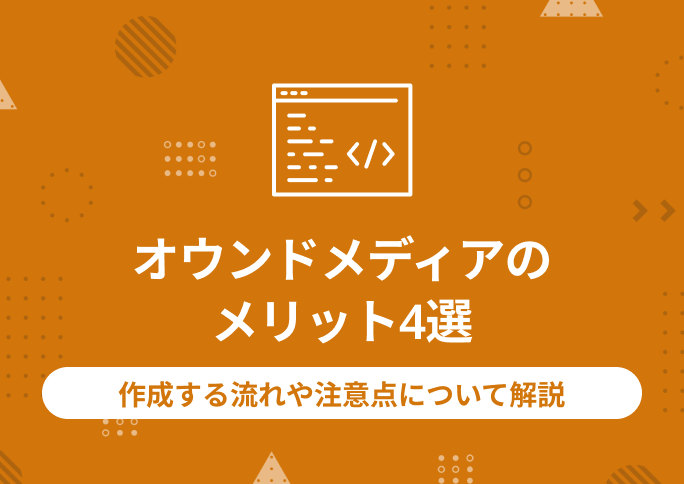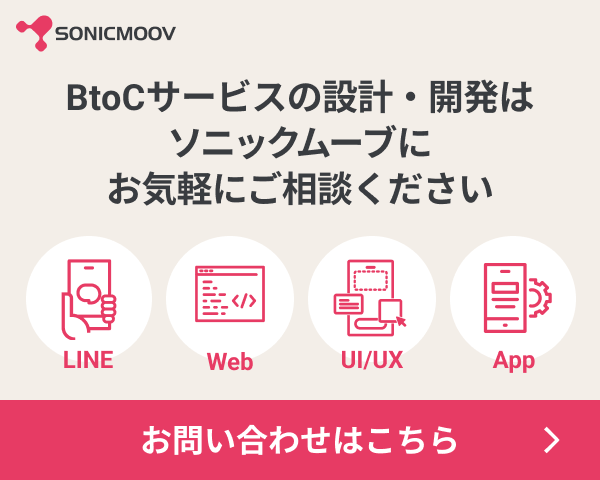昨今は、ビジネスにおけるマーケティングやブランディングの重要性が増しています。マーケティングやブランディングの手法はさまざまですが、そのうちの1つがオウンドメディアの運用です。
本記事では、オウンドメディアの概要をはじめ、メリットや作成の流れについて解説します。成功事例も一緒に取り上げるため、興味を持った方はぜひ最後までご覧ください。
目次
オウンドメディアとは

そもそもオウンドメディアとは、自社が保有しているメデイアの総称です。しかし、実際にはブログや情報発信のためのメディアという意味で使用されるケースが多いです。
主な運用目的として、集客や接触機会の増加、周辺情報の発信などが挙げられます。
ホームページとの違いは?
ホームページとは、ターゲットや訴求内容、目的などが異なります。オウンドメディアは、潜在層を含む幅広いユーザーがターゲットであり、自社サービスや商品の認知拡大が主な目的です。
一方のホームページは、顕在ニーズを持つ見込み顧客がターゲットであり、企業情報や採用情報の発信が主な目的です。
オウンドメディアのメリット4選
以下では、オウンドメディアの主なメリットについて解説します。
マーケティング費用の最適化
自社の情報を発信するにあたって、即効性があるWeb広告やペイドメディアを利用する企業は多いですが、自社の情報を発信するために広告費がかかる点がデメリットです。
しかし、自社のメディアであるオウンドメディアを利用すれば、余計な費用はかかりません。
潜在顧客への認知拡大と接触
一般的なホームページは、顕在化している顧客を対象に情報発信を行っています。一方のオウンドメディアは、KWの設定次第で潜在顧客に対してアプローチがしやすいです。
たとえば、食品メーカーが「お菓子作り 難しい」というKWでコンテンツを作った場合、お菓子作りが難しくて悩んでいる方に向けてお菓子を簡単に作れるキットや既製品のお菓子の宣伝ができます。また、検索エンジンの上位に作成したコンテンツを表示させることができれば、多数のユーザーの流入も期待できるでしょう。
ブランドの強化
企業イメージ向上のためにも、ブランディングは重要です。商品やサービスの販売のみならず、ユーザーの課題解決においても貢献してくれる企業と思ってもらえるためです。
そのためには、オウンドメディアを通じて、質の高いコンテンツを安定して供給し続けるのが有効です。
優秀な人材の発掘
昨今は、オウンドメディアリクルーティングと呼ばれる手法に注目が集まっています。
オウンドメディアリクルーティングとは、その名のとおりオウンドメディアを活かした人材採用です。
企業において、採用した人材がミスマッチによって離れるのは珍しい話ではありません。
しかし、採用のたびにコストがかかってしまうのは、あまり経済的とはいえません。
もしオウンドメディアを介して自社が求める人材や採用後の働き方を積極的に発信すれば、自社が求める人材を確保しやすくなります。
オウンドメディアのデメリット3選
オウンドメディアには、メリットだけでなくデメリットも存在します。具体的なデメリットの一覧は、以下のとおりです。
成果が出るまでの時間
オウンドメディアを運用しても、すぐに求めている結果は出ません。良質なコンテンツを長期間安定供給しなければ、検索エンジンから優良サイトと判断されません。
そのため、数ヶ月単位で時間がかかる覚悟を持つ必要があります。
初期の構築と運用
オウンドメディアの構築や運用には、専門知識が必要です。とくにサイト作りやプログラミングの基礎をまったく知らない場合は、難易度が跳ね上がります。
場合によっては、CMSをはじめとする労力を軽減するツールの採用を検討した方がよいでしょう。また、構築後の運用の手間も考慮してください。
人的リソースが必要
人手がなければ、優良なコンテンツの発信は続けられません。企業によっては、オウンドメディアの更新専門のチームも立ち上げるケースもあります。
もし適任がいなければアウトソーシング、つまり外部から人を雇うのもおすすめです。ただし、追加で人件費ががかかってしまいます。
オウンドメディア作成の流れ

オウンドメディアの作成は、以下の流れで行います。
ペルソナとコンセプトの設計
まずはペルソナ、オウンドメディアを利用するユーザー像を設定します。年齢や家族構成や趣味など、ディテールまでしっかり考えましょう。
ペルソナの設定が終わったら、次はコンセプトの設計を行います。これは方向性がぶれてしまうと、検索エンジンの評価が上がらないためです。
なお、ペルソナの設定方法は過去記事でも取り上げているため、気になった方は以下の記事を参考にしてください。
ペルソナ設定の方法を3ステップで解説!基礎知識から注意点まで
制作と運用の体制構築
オウンドメディアの各種設定が完了したら、ツールや外注先の選定を行いましょう。
あらかじめ運用計画を立てておくと、スムーズに選定を進められます。また、予算やスケジュールも、この段階で考えるとよいでしょう。
カスタマージャーニーの作成
カスタマージャーニーとは、顧客が商品やサービスを知り、購入するまでの流れを旅にたとえたものです。適切にオウンドメディアを運用していくために必要なため、真剣に取り組みましょう。
なお、カスタマージャーニーマップの作り方と注意点について、過去記事で取り上げています。気になった方は、以下記事を参考にしてください。
カスタマージャーニーマップとは?作り方6ステップと注意点を解説
対策キーワードの選定
ペルソナやコンセプトに合わせて、対策キーワードを決定します。対策キーワードの選定をする際は、キーワードプランナーの使用がおすすめです。
検索ボリュームが大きいKWは、上位を獲得できれば流入が期待できます。ただし、その分競合も多いため、バランスを考えましょう。
サイトおよびコンテンツの制作
準備が整ったら、実際にサイトを制作します。コンテンツの制作も同時に進めると。サイトが完成次第すぐに公開できます。
オウンドメディアの成功事例
最後に、オウンドメディアの成功例について解説します。
サイボウズ式の事例
グループウェアや業務改善サービスを提供している企業です。「新しい価値を生み出すチームのメディア」をコンセプトに、さまざまなコラムやインタビューを掲載しています。
オウンドメディアを介して働き方やチーム力のアップデートを示しつつ、企業全体のブランディングにも成功しています。
ジモコロの事例
複数の企業で運営されている共同運営するオウンドメディアです。主に地元愛を感じられる、ローカルネタのコンテンツを発信しています。
その結果、求職者に対して「地元の求人情報に強い」というイメージを醸成し、求人応募数の増加につなげることに成功しました。
グーネットマガジンの事例
グーネットマガジンは、株式会社プロトコーポレーションのオウンドメディアです。新車の情報をはじめ、自動車に関する総合的なお役立ち情報を発信しており、ユーザーのLTVの向上に寄与しています。
まとめ
以上、オウンドメディアのメリットやデメリット、成功事例について取り上げてきました。
オウンドメディアの運用は、コストパフォーマンスも高い手法です。ただし、ある程度専門知識が必要なため、サイトやコンテンツを用意するにあたって外注する方も一定数います。
ソニックムーブでも、過去にオウンドメディアの制作を請け負った経験があります。制作の流れや成果について過去記事でも取り上げているため、興味を持った方はぜひ以下の記事を参考にしてください。
デジタル領域でのお困り事やプロダクト開発について、まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせはこちら